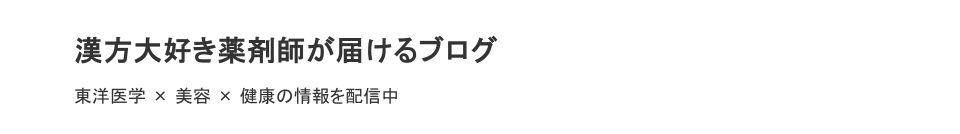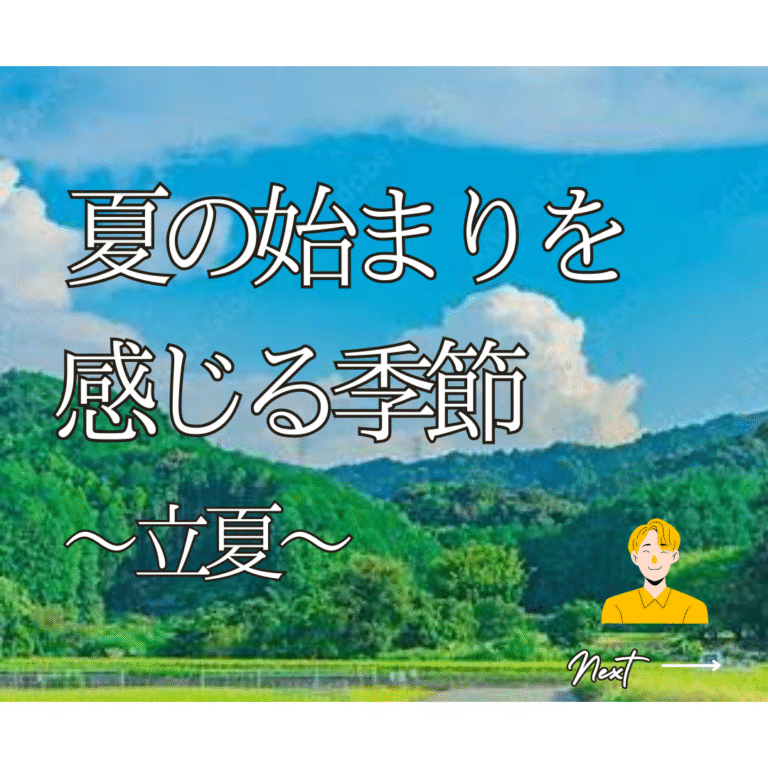はじめに
5月5日前後は、立夏(りっか)。
暦のうえでは「夏の始まり」とされるこの日、 実は、体も心も大きく変化するタイミングなんです。
- 春の疲れがどっと出る
- やる気が空回り
- 気温差で体調を崩しやすい
こんな時期だからこそ、
中医学の養生法で心と体を整えて、 次の季節を軽やかに迎えませんか?
この記事では、立夏の意味、なぜ不調が起きやすいのか、 そしてこの時期におすすめの食養生・生活習慣を詳しくご紹介します。
立夏とは?
二十四節気の7番目にあたり、毎年5月5日頃に訪れることが多い「立夏」ですが、年によっては5月6日になることもあります。
この日を境に、季節は春から夏へと切り替わります。
まだ肌寒い日もありますが、
- 木々が青々と茂り始める
- 日差しが強くなる
- 夏野菜が育ち始める など、自然界はすでに夏支度を始めています。
中医学では、“陽気(ようき)”がどんどん高まる季節。
心身が陽気についていけず、バランスを崩しやすい時期とも言われています。
立夏に起こりやすい心と体の不調
- 疲れやすい、だるい
- イライラする、気分が落ち着かない
- 食欲がない、胃もたれ
- 睡眠の質が落ちる
これらは、春から夏への季節の切り替えに、心と体が追いついていないサイン。
特に「肝(かん)」や「心(しん)」のバランスが崩れやすく、 気の巡りや血の流れが乱れがちに。
立夏の養生法〜体と心を整える習慣
🔸 1. 気の巡りを良くする食養生
- 香り野菜(しそ・セロリ・春菊)でストレスを緩和
- 酸味のある食材(梅干し・柑橘類)で気を整える
🔸 2. 「心」をやさしくいたわる
- 緑茶・菊花茶・ジャスミンティーでリラックス
- 夜更かしは控えめに(22時〜23時就寝が◎)
🔸 3. 軽めの運動で陽気を巡らせる
- 朝の散歩、深呼吸、ストレッチ
おわりに
立夏は、季節の変わり目。
体調や気持ちが揺らぎやすいのは、自然なことです。
だからこそ、無理せず、やさしく整えることが大切。
次の季節を軽やかに迎える準備を、今からはじめてみませんか?