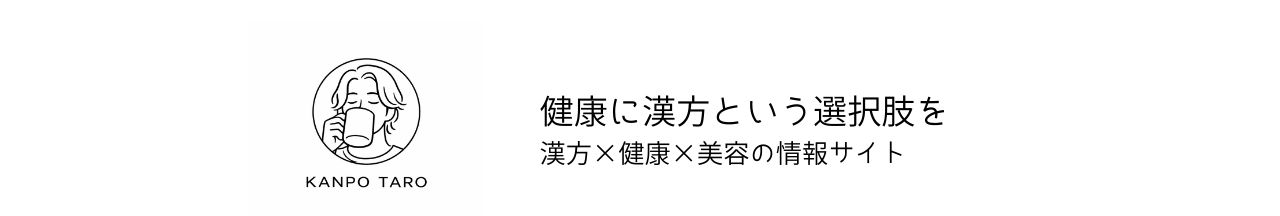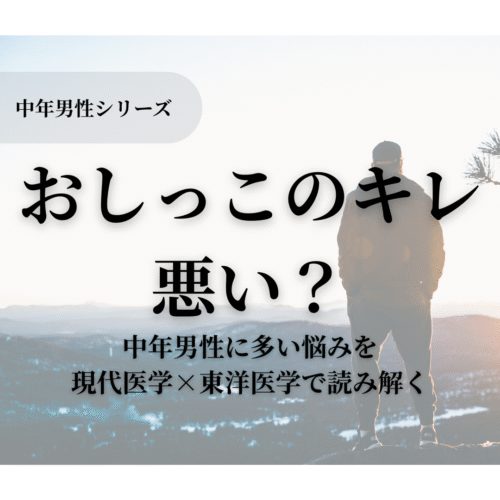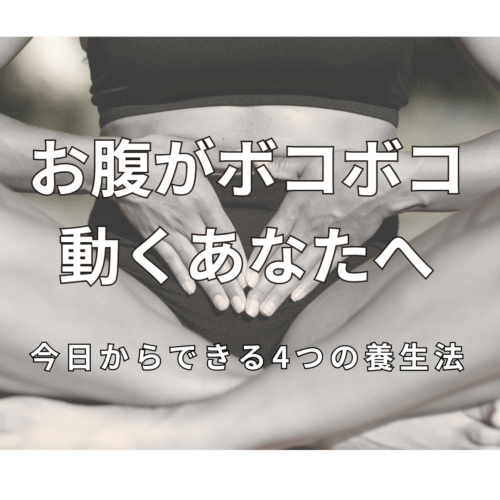――中医学で「肺」と「潤い」を整える、生活養生と漢方――
はじめに
朝晩の涼しさとともに、くしゃみ・鼻水・鼻づまり・のどのイガイガ・肌のカサつきが増える——「秋の花粉かな?」と思ったら、
まずは生活養生で土台を整え、必要に応じて漢方でやさしくサポートしていきましょう。
中医学では秋は燥(乾燥)が強まり、鼻・のど・皮膚を司る肺がゆらぎやすい季節。
今日から実践できる養生と、対症(つらい時)/体質改善(根本)の漢方の使い分けを、薬剤師の視点でまとめました。
中医学の基本
- 肺は皮毛を主る:鼻・のど・皮膚の粘膜は“肺”のテリトリー。乾燥でバリア(衛気)が弱ると刺激を受けやすくなります。
- 風燥:風に乗る花粉+乾燥の組み合わせ。粘膜がカサつき、ムズムズや咳が出やすい。
- 脾のケア:食から気(エネルギー)と津液(うるおい)を作る台所。冷たい・甘いの摂りすぎは長引く不調のもと。
※用語ミニ解説:衛気=体表のバリア力/気=エネルギーの流れ/津液=体のうるおい
セルフチェック
当てはまるほど、「肺のうるおい」と「バリア力」のケアが役立ちます。
生活養生(項目を分けて記載)
1)環境・習慣
- 湿度50〜60%を目安に加湿。エアコンの直風は避ける。
- 外出時はマスク+メガネで物理バリア。帰宅後は生理食塩水で鼻洗浄。通常の水でもOK。
- 水分摂取はちびち。一気飲みは体を冷やしやすい。
- 入浴は38〜40℃で10〜15分。のぼせやすい人は短めに。
2)呼吸・睡眠
- 朝3分の鼻呼吸散歩(背すじを伸ばしてゆっくり吸う・吐く)。
- 就寝1〜2時間前はスマホ控え、副交感神経を優位に。
- 口呼吸傾向の方は唇を閉じ舌を上顎へ(舌位の意識)。
3)食養生(潤い+健脾)
4)体質別の習慣のポイント
- 乾燥タイプ:加湿+潤い食材を少量ずつこまめに。長風呂は控え、保湿を丁寧に。
- バリア不足タイプ(気虚):睡眠最優先、朝日を浴びる、温かい食事。
- ストレスタイプ(肝鬱):深呼吸1分×3回/肩甲骨を動かす/カフェインは午後控えめ。
- 水たまりタイプ(痰湿):腹八分・揚げ物減らす・入浴で発汗スイッチ。
漢方の紹介
ご注意:以下は一般的な使用例です。体質・症状・持病・併用薬により適否が分かれます。自己判断での長期服用は避け、医師・薬剤師・専門家にご相談ください。妊娠・授乳中や、麻黄・附子・甘草など特定生薬を含む処方は特に慎重に。
A. 対症(つらい時の短期サポート)
B. 体質改善(中長期のベースづくり)
選び方のコツ
① まずは今のタイプ(乾燥/気虚/ストレス/痰湿)に合わせる
② 1〜2週間で“過ごしやすさ”の変化を観察
③ 併用薬(降圧薬・利尿薬・ステロイド等)や既往症は専門家に要確認
西洋医学と併用
- 一般に、非鎮静性抗ヒスタミン薬・点鼻ステロイド・生理食塩水による鼻洗浄・アレルゲン免疫療法が選択肢。
- 受診の目安:発熱・強い倦怠感・息苦しさ・嗅覚味覚の変化、強い充血や痛み、皮膚症状の急拡大など。
- 妊娠・授乳中、持病や内服中の方は自己判断での追加薬・サプリは控え、医療者に相談を。
まとめ
- 秋は「肺」と「潤い」がテーマ。
- 生活養生で土台を整え、つらい時は対症、落ち着いたら体質改善へ。
- 完璧を目指さなくて大丈夫。できることを1つ続けるだけで、秋はもっと楽になります。
今日の一歩:朝の鼻呼吸散歩3分+帰宅後の鼻洗浄。
早めに対策して、できることから始めていきましょう!!