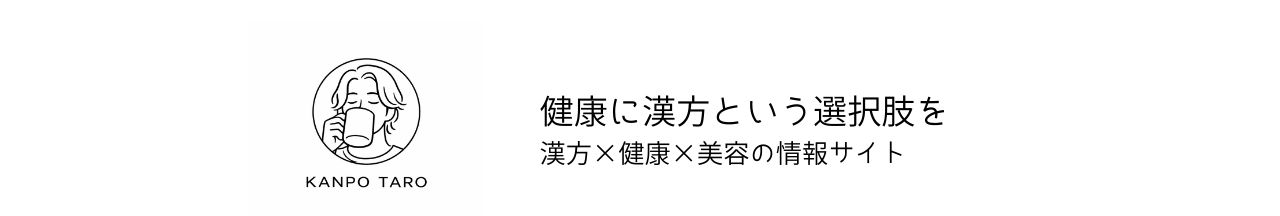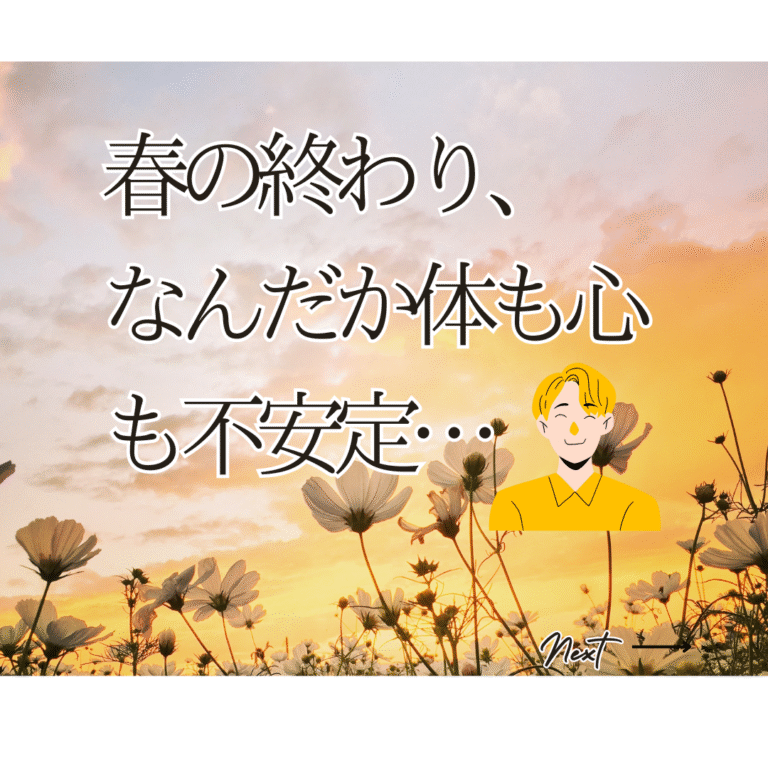はじめに
春が終わる頃、こんな不調はありませんか?
- なんとなく疲れやすい
- 胃腸が弱っている気がする
- 情緒が安定しない、そわそわする
それ、“春の土用”のせいかもしれません。
中医学では、四季の変わり目に当たる「土用」は体調が崩れやすく、
特に脾(ひ)=消化器系が最もダメージを受けやすい時期とされます。
この記事では、春の土用の意味・不調の理由・養生法まで、 中医学の視点で詳しく解説します。

春の土用とは?
「土用」とは、暦のうえで四季の変わり目に訪れる18〜19日間のこと。
- 春の土用:4月中旬〜5月初旬(立夏の直前)
- 土の気=“脾”に関わる期間で、五臓のうち「脾胃」が乱れやすい
土用期間は、
“前の季節の疲れ”が出やすく、
“次の季節に切り替える準備”
の時期とも言われています。
春の土用では、特に「春の疲れ」が脾に現れやすいのが特徴。
春の土用に起こりやすい不調
- 食欲不振/胃のもたれ/下痢・軟便
- 倦怠感/だるさ/やる気が出ない
- 気分の落ち込み/焦り/そわそわ感
中医学では、脾は「運化(うんか)」=飲食物をエネルギーに変える力を司ります。
この運化機能が落ちることで、気が生まれず、体も心もパワーダウン。
春の土用の養生法
🔸 1. 胃腸を守る食事
- よく噛む・温かい食事・腹八分目
- 豆腐、かぼちゃ、山芋、じゃがいも、米などの“脾を補う”食材
- 冷たいもの、生もの、脂っこいものは控えめに
🔸 2. ストレスをためない・ゆっくり過ごす
- 睡眠をしっかりとる
- 軽めの運動で気の巡りを促す
- 気分転換・笑う・深呼吸を意識
🔸 3. 中医学的ケア(補脾薬)
- 補中益気湯、六君子湯、参苓白朮散など、気を補い胃腸を整える漢方が◎
- 症状や体質に合った処方を選ぶのがポイント
おわりに
季節の変わり目は、ただ「気候が変わる」だけではなく、 体も心も“次の季節”に適応するための調整期間です。
「春の土用」のような時期は、 「頑張る」ではなく「緩める」「いたわる」時間を大切にしてみてください。
日々のちょっとした選択で、次の季節を心地よく迎えることができます。