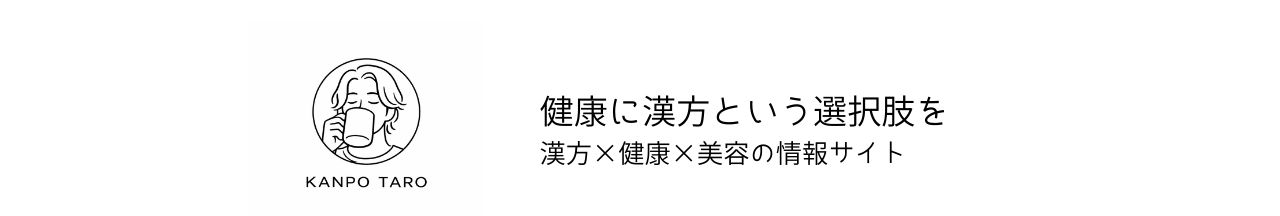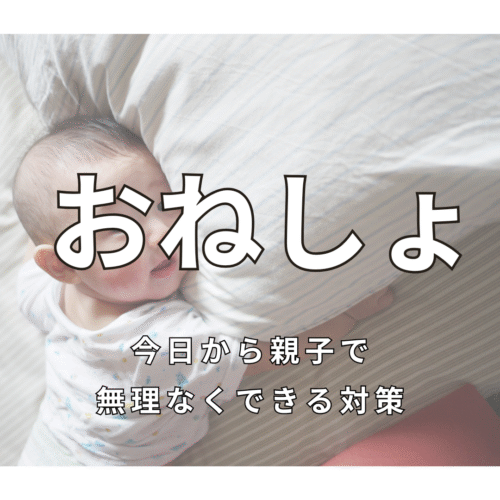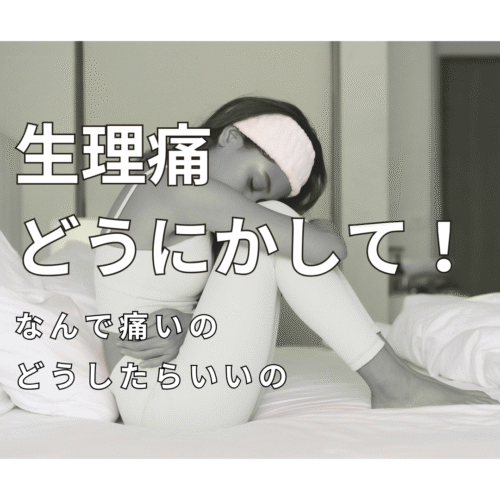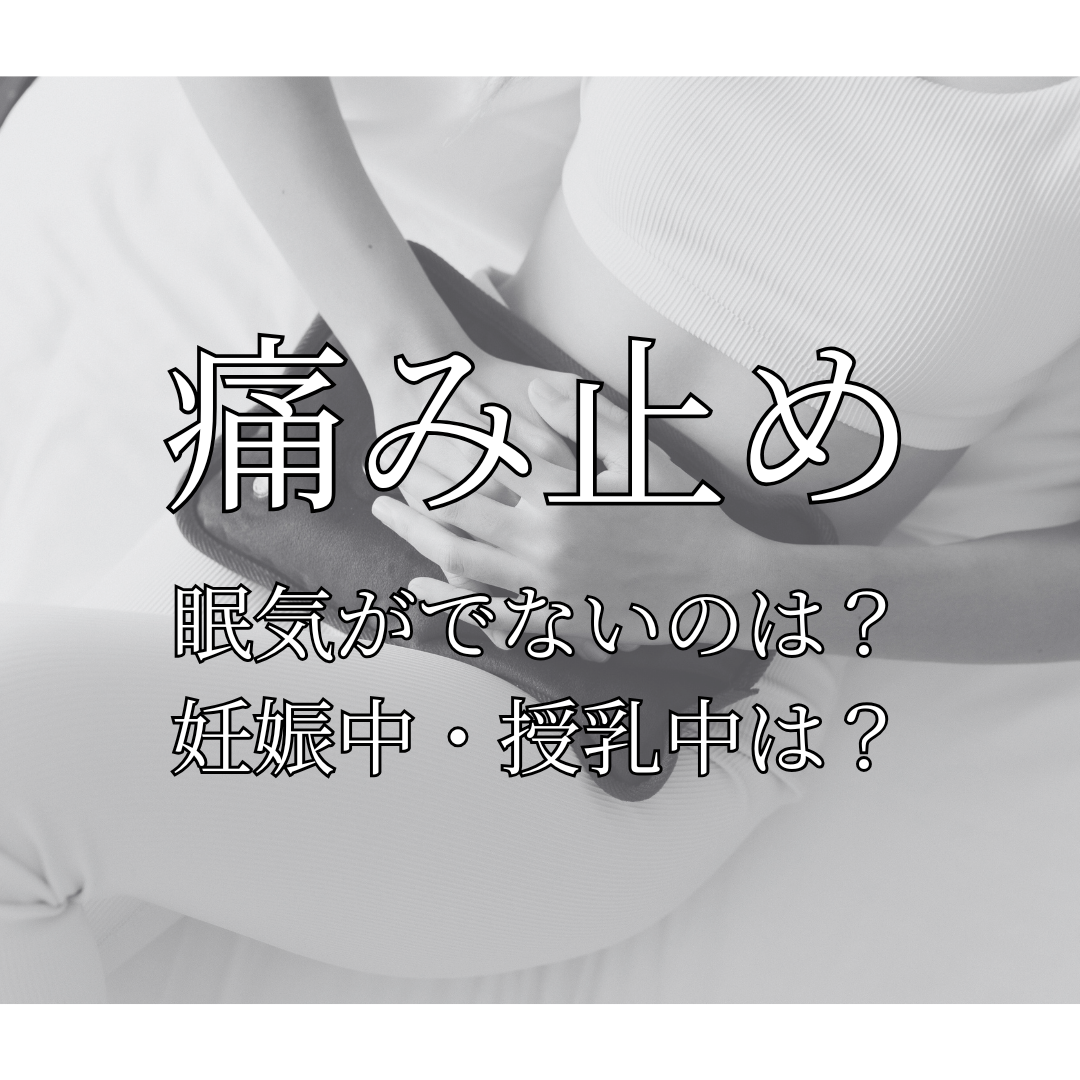3〜5歳頃の子供っておねしょおおいですね^^;
朝から「毎朝の洗濯がつらい」「叱りたくないのにイライラしちゃう」
ってことはよくあることですよね。
この3〜5歳のおねしょは発達の途中でよくあるサインなんです。
おねしょをしてしまう原因や中医学で見たときの体質のチェックや漢方の使用例を紹介します。
日常で簡単に取り得れる今日から親子で無理なくできる対策をのせてます。
叱るより“整える”で親子でおねしょを乗り越えていきましょう。
おねしょの基礎
- 呼び名:医学的には「夜尿」。5歳以降も続く場合は「夜尿症」と呼びます。
- よくある背景
- 夜の尿量が多い(体内リズムやホルモンの未熟)
- 膀胱の発達途中/我慢ぐせ
- 深い眠りで尿意に気づきにくい
- 便秘・ストレス・生活リズムの乱れ
中医学のやさしい見方
中医学では“水のめぐり”を司るが腎(じん)、消化吸収を司るのが脾(ひ)。
子どもは「脾常不足(消化が未熟)」「腎常不足(発達途中)」がベースです。
- 腎気不固タイプ:疲れやすい/冷えやすい/尿回数が多い・夜に漏れやすい
- 脾肺気虚タイプ:風邪をひきやすい/食ムラ・軟便/朝ぼんやり
- 湿熱タイプ:甘い・冷たいものが多い/尿の色・ニオイが濃い/肌トラブル
※タイプは目安。自己判断での服薬は避け、必ず医療者・専門家に相談してください。
今日からできる7つの生活ケア
10分で整う薬膳ヒント
体質のヒントと漢方の考え方(例)
体質や年齢、症状によって可否・用量が変わります。自己判断での服用は避け、小児科・漢方の専門家へ。
かんたんセルフチェック(3〜5歳向け)
当てはまるものにチェック。多い項目が“体質のヒント”です(診断ではありません)。
よくある質問
Q. 3〜5歳なら様子見でOK?
A. “よくある”年齢です。心配が強い時は気軽に小児科へ。
Q. 叱った方が直る?
A. 叱ると逆効果。成功した日を一緒によろこぶ方が近道です。
Q. 水分は厳しく制限する?
A. 昼は十分、夕方以降だけ控えめが基本。脱水はNG。
まとめ——できることから、で大丈夫
自分のこどもはこのタイプかなってありましたか?
ひとつでも「できそう」があれば十分です。
親子のペースでゆっくり整えていきましょう。
保存して、つらい朝に読み返してくださいね。