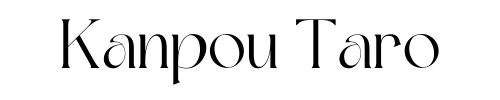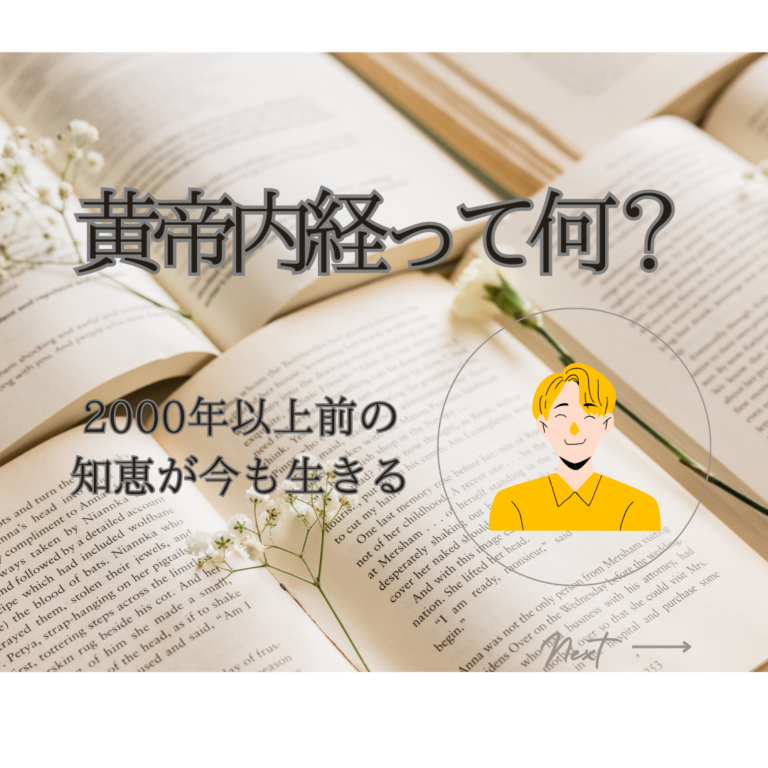はじめに:黄帝内経とは?
「黄帝内経(こうていだいけい)」は、
約2000年以上前に成立したとされる中医学の基礎となる古典です。
黄帝(伝説の帝王)が、
名医・岐伯と問答しながら医学の原理を解き明かしていく形式で書かれています。
この書は、人体の仕組みや病気の原因、治療法、養生法などを詳しく説明し、
現在の中医学の理論の土台になっています。

「黄帝内経」の構成
「黄帝内経」は、以下の2つの書物から成り立っています。
- 素問(そもん):
- 生命の仕組みや、病気の原因、診断法などを解説。
- 「五臓六腑」「陰陽」「気血」「経絡」など、中医学の基礎概念が書かれている。
- 霊枢(れいすう):
- 経絡(けいらく)やツボ(経穴)について詳しく解説。
- 鍼灸治療の理論や技法が記されている。
黄帝内経の重要な考え方
✅ 陰陽(いんよう)
- 自然界も人体も「陰」と「陽」のバランスが重要。
- 陰陽の調和が崩れると病気になる。
✅ 五行(ごぎょう)
- 木・火・土・金・水の5つの要素が人体や自然の変化を表す。
- 五臓(肝・心・脾・肺・腎)との関係が深い。
✅ 気・血・津液(しんえき)
- 気(生命エネルギー)、血(血液)、津液(水分)の流れが健康を維持する。
- これらが滞ると病気の原因になる。
✅ 経絡(けいらく)
- 気血が流れる道。
- 経絡の滞りを解消することで健康を維持できる。
✅ 養生(ようじょう)
- 健康を維持するための日常生活の工夫。
- 食事・睡眠・運動・感情のコントロールが重要。
現代にも役立つ黄帝内経の知恵
黄帝内経は単なる古典ではなく、
現代の健康管理にも活かせる知恵が詰まっています。
✔ 季節に応じた養生法(春は肝を整え、夏は心を守る)
✔ 病気の予防を重視する考え方(未病を防ぐ)
✔ 自然と調和した生き方(体のリズムに合わせた生活)
まとめ
「黄帝内経」は、単なる医学書ではなく、
生命の法則や健康を守るための知恵が詰まった書です。
現代においても、日々の養生や病気予防に役立つ考え方がたくさんあります。
これを機に、黄帝内経の知恵を日常生活に取り入れてみてはいかがでしょうか