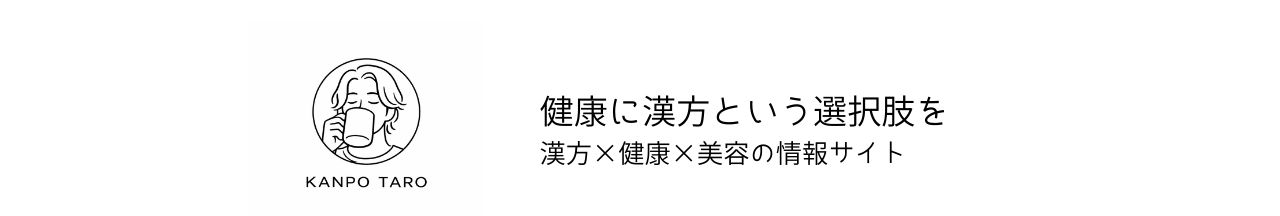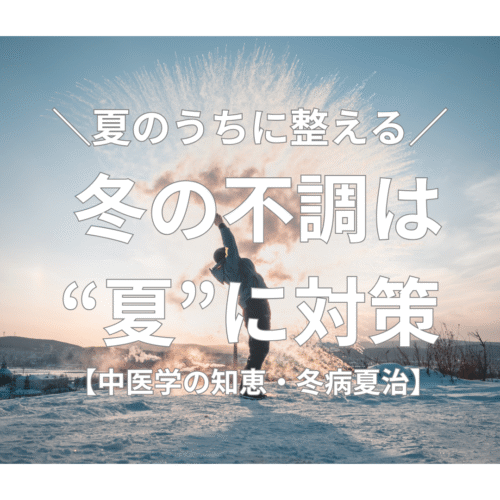中医学×栄養学で見つけた“ちょうどいい飲み方
コーヒーって体にいいの?悪いの?迷い続けた私
「朝はコーヒーがないと始まらない」
「でも最近、飲むとお腹が冷える気がする…」
「カフェイン、やっぱり摂りすぎかな?」
そんなふうに、
日常に寄り添ってくれるコーヒーだけど、ちょっと気になることもある。
そこで今回、コーヒー好きの私が
中医学と現代栄養学の視点から、本気でコーヒーのことを調べてみました。
中医学でみた「コーヒーの正体」
中医学では、飲み物にも「性質」や「体のどこに効くか(帰経)」があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 性味 | 甘味・苦味・渋味 |
| 性質 | 温性(体を温める) |
| 帰経 | 心・肺・胃に働きかける |
| 主な働き | 脳をシャキッと、心を元気に、余分な水を出す |
つまりコーヒーは、
☑️気の巡りをよくして覚醒を促す
☑️体内の余分な水分を排出する(利尿)
☑️内臓、とくに「心」に刺激を与えて元気を出す
でも同時に、“潤いを乾かす”という側面もあることに注意が必要です。
西洋医学からみたコーヒーのチカラ
コーヒーの「すごいところ」は、現代栄養学でも明らかになっています。
カフェインのパワー
- 覚醒作用で集中力アップ
- 心臓の動きをサポートして血流促進
- 腎臓に作用して利尿作用(むくみにも◎)
ポリフェノール(クロロゲン酸)
- 強い抗酸化作用で、老化の原因「酸化」をブロック
- 血糖値の上昇を緩やかにする働きも
腸への刺激
- 適量なら腸のぜん動運動を活性化し、便秘の人にも◎
ベストな「飲むタイミング」は?
コーヒーの良さを最大限に活かすには、タイミングが命!
朝〜午前中(超おすすめ)
- 「陽の気」が上がる時間とコーヒーの温性がマッチ
- 朝食後に飲めば胃を守りつつ覚醒力もアップ!
昼食後(まあまあおすすめ)
- 食後のコーヒーは、消化をサポートしながらリフレッシュ
- ただし、食前の空腹時は胃に負担がかかるのでNG
夕方以降(控えたい)
- 副交感神経への切り替え時間にカフェインは逆効果
- 15時以降のコーヒーは、睡眠の質に影響するかも
コーヒー、こんな人は“ちょっと注意”
冷え性・胃腸虚弱タイプのあなたへ
中医学では、「苦味・渋味」は体の潤いを消耗しやすい性質とされています。
また、胃腸が弱いタイプの方は「気」や「陰」が不足しがちなので、
コーヒーが余計に消耗を進めてしまう可能性も。
さらに現代医学でも、
- カフェインが胃酸分泌を促しすぎて胃に刺激を与える
- 利尿作用でミネラルが排出され、冷えを悪化させる
といった注意点があります。
こんな症状がある人は、量や飲み方を見直してみて
- 朝、コーヒーを飲むとお腹がゴロゴロする
- 食後でも胃がムカムカする
- 手足の冷えが気になる
- 寝つきが悪い or 夜中に目が覚める
「体にやさしいコーヒー習慣」4つのヒント
| 工夫 | 理由 |
|---|---|
| 食後に飲む | 胃への刺激を減らすため |
| 温かい状態で | アイスよりホットが胃腸にやさしい |
| 1〜2杯が目安 | 飲みすぎると“陰”を削る恐れも |
| 疲れた日は無理に飲まない | 白湯や黒豆茶に置き換えるのも◎ |
「コーヒー=元気の前借り」になってない?
疲れていても、つい「これ飲めばがんばれる」と手が伸びる。
でも、本当はその疲れ、コーヒーじゃなく“休息”が必要なのかもしれません。
コーヒーは、体の声を無視して無理をするための道具じゃない。
“暮らしに寄り添うパートナー”として、ちょうどよく付き合うのがいちばん素敵。
まとめ:コーヒーは「飲み方」で変わる
- 中医学では、コーヒーは「温性・甘苦渋味・心肺胃に作用」
- 巡りを助け、脳や心を元気にしてくれる飲み物
- でも体質や時間帯によっては“負担”になることも
- 自分の体に合った「量・タイミング・飲み方」がカギ!
「コーヒーをやめる」じゃなくて「コーヒーと上手に付き合う」が、今日からの新習慣。