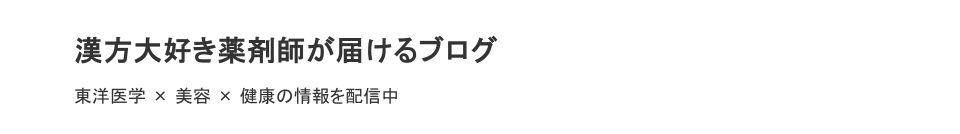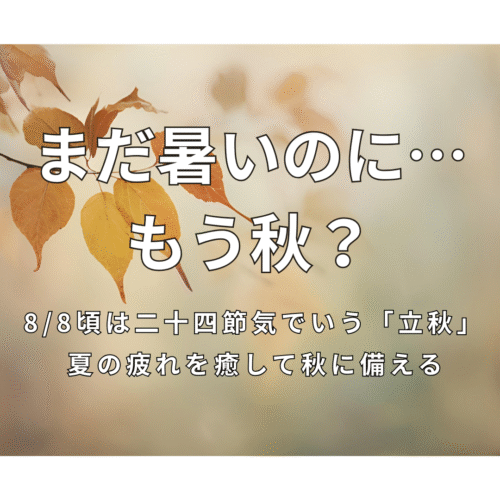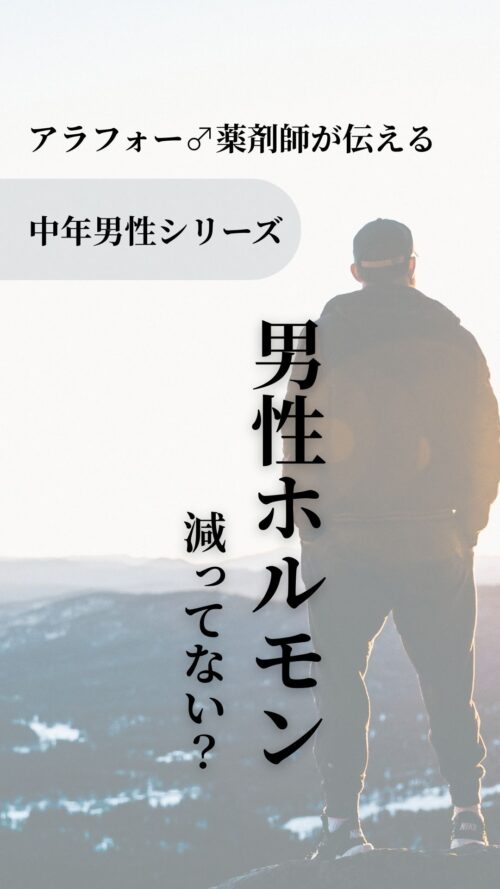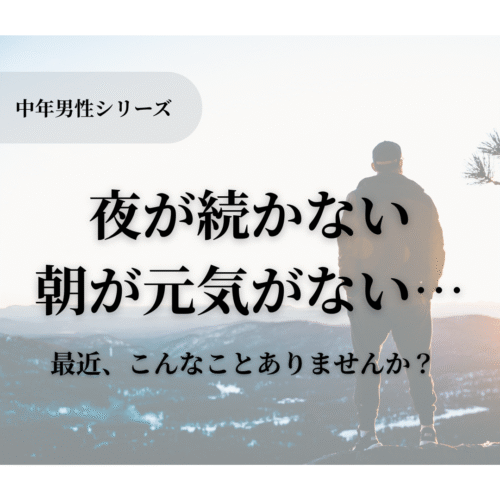〜二十四節気と中医学でみる、8月8日前後の過ごし方〜
はじめに
8月8日頃は、二十四節気でいう「立秋(りっしゅう)」にあたります。
「え?まだ全然暑いのに秋?」と思われる方も多いですが、暦の上ではここから秋が始まります。
立秋は、夏から秋への季節の変わり目。
中医学では、季節の変わり目は 脾(ひ)や肺(はい) の働きが乱れやすく、体調を崩しやすいと考えます。
特にこの時期は「残暑」と「湿気」が大きな負担になり、夏の疲れが表面化してくるタイミングです。
この記事では、立秋に意識したい養生ポイントと、今日からできる簡単なケア方法をお伝えします。
立秋と中医学の関係
二十四節気は、季節の移ろいを細かく示す暦で、立秋はその第13番目。
この時期のキーワードは 「暑さの中に潜む秋の気配」 です。
中医学では、秋は「肺」と関係が深く、乾燥や冷えに弱い季節。
でも、立秋直後はまだ暑く湿気も多いため、
肺を守る前に「余分な湿と熱」を取り除き、体の巡りを整えておくことが大切です。
この時期に起こりやすい不調
- 体がだるい・重い
- 食欲不振
- 胃もたれ
- 下痢や軟便
- むくみ
- 立ちくらみ
- 夏の疲れによる肌荒れや吹き出物
これらは「脾胃(消化器系)」が湿気や冷たい物で弱っているサイン。
また、夏に消耗した「気(エネルギー)」が足りず、免疫力が下がっていることも多いです。
立秋の養生ポイント
1. 残暑対策と“冷やしすぎ”の防止
まだ暑いからといって冷たい飲み物や食べ物ばかり取ると、脾胃が弱まり、秋口の不調の原因になります。
冷たい物は控えめにして、常温や温かい飲み物を意識しましょう。
2. 湿気を追い出す食材
脾胃を整えながら湿気を取り除く食材をおすすめします。
- はと麦
- 冬瓜
- トウモロコシ(ひげも)
- 小豆
- きゅうり(※生食は控えめ、軽く火を通すと◎)
3. 気を補う食材で疲労回復
夏の疲れは「気虚(ききょ:エネルギー不足)」の原因になります。
- 山芋
- 黒豆
- 鶏肉
- かぼちゃ
- 枸杞の実
4. 秋の乾燥に備える
残暑が和らぎ始めたら、肺を潤す食材に少しずつ切り替えます。
- 梨
- 白きくらげ
- はちみつ
- 蓮の実
今日からできる簡単薬膳スープ
はと麦とトウモロコシのスープ
【材料(2〜3人分)】
- はと麦(乾燥)…30g
- トウモロコシ(生でも缶でも可)…1本分または100g
- 鶏むね肉…100g
- 生姜スライス…2〜3枚
- 塩…少々
【作り方】
- はと麦は軽く洗って30分ほど水に浸す。
- 鍋に水800ml、はと麦、生姜、鶏肉を入れて中火で煮る。
- 鶏肉に火が通ったらトウモロコシを加え、さらに10分煮る。
- 塩で味を整えて完成。
※湿気を取りつつ、気を補って疲れを和らげます。
まとめ
立秋は、夏の疲れを癒し、秋に備えるための大切な季節の節目です。
まだ暑いからと油断せず、脾胃を守って湿気を取り除き、少しずつ秋の乾燥対策へシフトしましょう。
「できることから、少しずつ」。
日々の養生が、秋から冬を健やかに過ごすための土台になります。
一緒に健康な未来と作っていきましょう。